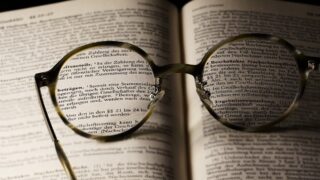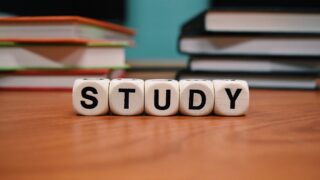※本記事はあくまで私自身の実体験です。
すべての方に当てはまるわけではありません。
参考程度にお読みいただけると嬉しいです。
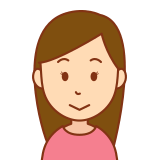
こんにちは!
現在4歳と5歳の年子育児中、ママ歴5年のMoyuです。
1歳5ヶ月差の兄妹を育てながら、毎日バタバタだけど笑いもいっぱいの毎日を過ごしています。
今回の記事では、年子育児0歳から3歳までのメリット・デメリットをまとめてみました!
私自身のリアルな体験をもとにお話します。
これから年子育児を迎える方、今まさに奮闘中の方の参考になれば嬉しいです!
年子のメリット

年子とは名前の通り、1歳差のきょうだいの事です。
上の子が1歳11か月の間に下の子が生まれると年子になります。
また出産する時期によっては、1学年差になったり、2学年差になったり、学年上は同級生になったりすることもあります。
我が家は1歳5か月差で1学年差になります。
年子育児は大変だと言われていますが、ほんとにその通りです!だけど年子で良かったなと思うこともたくさんあります!
では早速ご紹介していきたいと思います!
①赤ちゃん返りが少ない

我が家では、下の子が生まれたとき、上の子はまだ1歳5か月でした。
1歳5か月といえば、まだまだ赤ちゃん。
もし2歳以上年が離れていたら、上の子はある程度自分でできることが増えてきて、どうしても下の子に手がかかりがちになります。
でも、年子の場合は上の子もまだ手がかかる時期なので、「ママを取られた!」と感じる前に下の子が生まれたこともあり、寂しさはあまり感じなかったのではないかな?と思います。
実際、上の子もオムツ替えが必要でしたし、ミルク(ステップ)も飲んでいました。
だから、下の子と並んでオムツを替えたり、一緒にミルクを飲んだり…まるで双子のような育児でした。
第2子が生まれると、どうしても赤ちゃんに手がかかりますが、上の子の心のケアもとても大切ですよね。
②育児用品をそのまま回せる

第1子を出産して間もなく第2子が生まれたので、入院時に必要なものを新たに買い直すことなく、ほとんどそのまま使い回すことができました。
パジャマや下着などの入院グッズもまだ新しくきれいだったので、そのまま活用。
おくるみやベビードレス、新生児期に着ていた服も同様に下の子に回しました。
性別が違ったので少しだけ買い足しましたが、年が離れていれば一から揃える必要が出てきたと思います。
子どもの成長は早く、サイズアウトした服やズボンもすぐに下の子に使えるので、収納や保管に困ることもなくスムーズ。
「もう流行ってないかも…」という心配もなく、きれいな状態で使えるのでとても経済的です。
さらに、片づける間もないうちに次の子に使えるので、保管場所に悩むこともありません。
余ってしまったオムツもすぐに下の子に回せるのは、本当に助かります。
③遊ぶ内容がほぼ同じで楽

年の差があると、上の子が細かいおもちゃやスライム、はさみなどを使うようになる頃、下の子がまだ何でも口に入れてしまう時期だと本当に大変ですよね。
我が家では年子だったこともあり、その点の心配は比較的少なかったように思います。
上の子が細かいビーズやおもちゃで遊ぶときは、下の子が寝ている時間を選んだり、テーブルの上だけで遊ばせたりしていました。
遊び終わったあとは、おもちゃが床に落ちていないか隅々までチェック。
神経は使いましたが、その時期も長くは続かず、下の子の成長とともにだんだんと気を遣う必要も減っていきました。
旅行やお出かけでも、年齢差が小さいと遊ぶ内容やレベルが似ているので行き先に悩むことが少なく、一緒に楽しめるのも嬉しいポイントです。
遊園地の乗り物なども、上の子が乗れるようになってから1年だけ待てば、下の子もすぐに一緒に乗れるようになります。
遊ぶおもちゃも年齢差が小さいのでほとんど同じものを共有でき、自然と一緒に仲良く遊んでくれるのが本当に助かります。
公園でも家の中でも、ふたりでずっと楽しそうに遊んでいる姿を見ると、年子育児の良さを実感します。
もちろん、なんでも口に入れてしまう時期は一瞬たりとも目が離せませんでしたが、それを乗り越えると、家事もスムーズに進められるようになり、ぐっとラクになりました。
④大変な時期がまとめて終わる

年子育児の大きな特徴は、
「大変な時期が一気に押し寄せること」。
でもその分、落ち着くのも早いんです。
歳の差が開いているとどうしても「どうしてたっけ?」と忘れてしまったり、上の子がやっと落ち着いてきたのにまた大変な時期を最初からになりますよね。
(逆に歳が離れていたら、下の子の育児をゆっくり堪能出来たのかなと想像することもあります。)
でも年子だと、1年後にまた同じことをするので、感覚も知識もそのまま“現役”で活かせます。
たとえば離乳食。
上の子のときは初めての育児で、離乳食を作るのも時間がかかって大変でした。でも下の子のときは、作り方や段取りがわかっていたので、すごくラクでした!
幼稚園や保育園の準備も、上の子と一緒に下の子の分も同時進行!
絵本バッグやお弁当袋もミシンを出すのは1回で済みます(笑)
作り方も一度作ってすぐ作るので「どうだったっけ?」という事がありません。
予防接種も、上の子の記憶が新しいうちに下の子の番が来るので、スケジュール管理もラク。通院期間もまとめて短く済むのは助かります。
一気に大変だからこそ、一気にラクになる
年子育児は、出産から数年間は本当に大変。
でも、下の子がイヤイヤ期を終えた3歳頃になると、一気に楽になったなと感じたことを覚えています。
もちろん子どもの性格や発達には個人差がありますが、我が家では「長いトンネルをやっと抜けた!」という感覚がこの頃にやってきました。
言葉も通じるようになり、自分でできることも増えてくる。
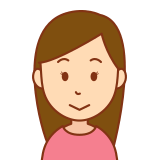
まだまだ手はかかりますが、2人そろってグンと成長してくれるのが、年子ならではの良さだと実感しました。
さらに、育児の大変なピークが重なることで、子育て全体の期間がコンパクトにまとまるというメリットも。
少しずつ自分の時間も持てるようになり、「第二の人生」を楽しむ準備も始めやすくなります。
また、子育て期間が短い分、老後資金や自分のキャリアなど、将来への準備を早めにスタートしやすいのも魅力です。
年子のデメリット
ここまで年子育児のメリットをたくさんご紹介してきましたが、もちろん大変なこともたくさんあります。
でもそれは、年子に限らず、何歳差であっても、1人っ子であっても、子育ては本当に大変ですよね。
そのうえで、「年子ならではの大変さ」も確かにあると感じています。
今回は、私が実際に感じた“年子育児の大変だったこと”についても、具体的にシェアしていきたいと思います!
①妊娠・出産で体がボロボロ

我が家の場合、上の子がまだ1歳になる前に、下の子の妊娠が発覚しました。
妊娠や出産は母体に大きな負担がかかりますよね。
年子を産むという事は、母体の体が完全に回復しないうちに赤ちゃんのお世話をしながら妊娠することになります。
精神的にも体力的にもかなりのエネルギーが必要です。
体調を崩してもなかなか回復しません。(これは年子関係なく産後あるあるかもしれません。)
髪の毛もたくさん抜けました。
私はつわりがひどかったので、常に袋を持ち歩きながら、睡眠不足と闘う毎日。
後追いや夜泣きがある中での妊娠生活は、本当に過酷でした。
我が家では、上の子が1歳の頃に卒乳し、ステップミルクに切り替えていたので授乳時期は重なりませんでしたが、もし重なっていたらさらに大変だと思います。
授乳の負担を減らすためにも、ミルクや哺乳瓶の活用はとても助けになります。
私は助産師さんから「おっぱいだけでなく哺乳瓶でも飲めるようにしておくと安心」とアドバイスをもらっていたので、新生児期から哺乳瓶にも慣れさせていました。
搾乳して哺乳瓶に取っておいたり、ミルクを足していました。
体調が優れないときや、ちょっとした外出の際にパパに預ける場面でも、哺乳瓶に慣れていると安心してお願いできます。
ただでさえ、大変な妊娠出産、そして育児。
初めての育児でわからないことだらけの中、夜間の授乳やお世話、慢性的な寝不足で、母体の負担は本当に大きかったです。
②連続で大きな出費が来る

- 幼稚園・保育園の準備
- 小学校入学
- 習い事
- 将来の進学費用
保育園、幼稚園の準備にかかる費用が連続でかかります。
これから小学校、高校、大学と進学していく際にも、連続で大きな出費がありますよね。
これらが2年連続でドンッと来るので、お金の計画が重要です。
年齢が離れていれば、貯められる期間が長いので比較的準備をしやすいとも言えます。
年子は連続で来る大きな出費に備えて資金計画をしっかり立てる必要があります。

0~4歳までの年子育児の大変だったことやどうやって乗り越えて来たかなどを載せています。
こちらもチェックしてみて下さい☆
まとめ
今回は、私自身の経験をもとに、年子育児のメリット・デメリットを0歳から3歳までの実体験をもとにご紹介しました。
年子育児は、体力的にも精神的にも大変です。
妊娠・出産の負担、連続する夜間の授乳や睡眠不足。
そして連続して訪れる出費。
だけどその一方で、
- きょうだい仲良く遊べること
- 育児グッズをそのまま使い回せること
- 遊びや生活リズムが揃いやすくて日常がスムーズなこと
- 育児のピークが一気に来て、一気に落ち着くこと
など、「年子ならではの良さ」も本当にたくさんあります。
今まさにバタバタの毎日で心が折れそうな方もいるかもしれません。
でも、必ず「少し楽になったな」「やってきて良かったな」と思えるタイミングが来ます!
このブログが、これから年子育児を始める方や、今まさに奮闘中の方の、ほんの少しでも励みになれたら嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!