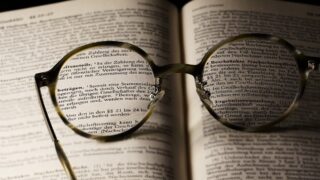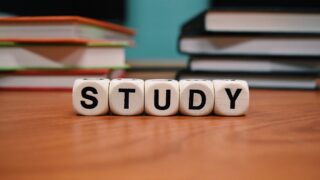※このページにはプロモーションが含まれています
本記事はあくまで私自身の実体験です。すべての方に当てはまるわけではありません。参考程度にお読みいただけると嬉しいです。
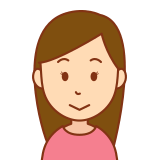
こんにちは!
現在4歳と5歳の年子育児中、ママ歴5年のMoyuです。
1歳5ヶ月差の兄妹を育てながら、毎日バタバタだけど笑いもいっぱいの毎日を過ごしています。
今回の記事では、
年子育児0歳から4歳までの年子育児で一番大変だった時期はいつ?年齢別にリアル体験と乗り越え方を紹介!

はじめに:年子育児で大変だった時期は?
現在、5歳(もうすぐ6歳)と7歳の年子きょうだいを育てている新米ママですが、つい最近まで怒涛の年子育児の真っ只中にいました。
「年子ってどの時期が一番大変?」「みんな、どうやって乗り切ってるの?」
そんな疑問に、自分の体験をもとに年齢別でリアルにお答えしたいと思います。
同じように年子育児を頑張っているママさんの参考になれば嬉しいです!
【妊娠中】つわりと育児のダブルパンチ

つわりがとにかくひどくて、出産当日まで吐き気と嘔吐が続きました。
上の子はまだ赤ちゃん。
夜泣き・授乳もあり、寝不足との戦いです。それに後追いも・・・
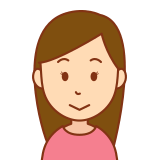
私の場合、一番つらかったのは妊娠期間中でした。
特につわりがひどくて、体調が悪い中でも上の子のお世話をしなければならず、本当に大変だったのを覚えています。
でも、同じ年子ママの友人は「つわりは軽かったけど、生まれてからの育児の方が大変だった」と話していたので、本当に人それぞれで個人差があるんだなと実感しました。
年子育児の大変さは、「どの時期に苦労するか」が人によって違うのも特徴かもしれません。
数分横になるだけでも全然違います。赤ちゃん+妊娠中という時期は、体力回復が最優先です。
それに上の子が寝たら一緒に寝れるのは、今だけ。
下の子が生まれたら寝ていられません(笑)
家事も気になるけど、いさぎよく寝るべし!
【上の子1歳/下の子0歳】

年子育児でよく聞くのが、「夜中のお世話が本当に大変!」という声です。
授乳やミルク、オムツ替えなどが上の子・下の子でダブルで発生すると、体力的にも精神的にもかなりの負担になります。
特に月齢が近くて、どちらも授乳や夜泣きがある場合は、ほとんど寝る時間がないというママも少なくありません。
我が家は1歳5か月差の年子だったため、ちょうど上の子が卒乳していたこともあり、授乳が重なることはありませんでした。
それでも、上の子と下の子の2人の生活リズムがズレると自分の睡眠時間はほぼ取れない…ということも。
どちらかが寝ても、もう片方が起きていたりすると、自分の休める時間がまったくないというのが、年子育児のリアル。
上の子がもう少し大きければ、下の子が寝たタイミングでママも一緒に目をつむって休む…ということもできますよね。
でも年子育児の場合、上の子もまだまだ手がかかる時期。動きも活発になってきていて、目を離すわけにはいきません。
そのため、下の子が寝ている間もママはずっと起きていて、なかなか休む時間が取れないのが現実です。
このタイミングでは、「家事は後回しにして迷わず一緒に寝る!」これが鉄則です。
…とは言え、現実はなかなかそうもいきません。
洗濯をサボれば着せる服がない
ご飯を作らないと誰も作ってくれない
家事はどんどん溜まっていく
私も「ちゃんとやらないと!」と必死に毎日こなしていました。
でも今思えば、もっとラクしてよかったのに…と思うこともたくさんあります。
今だから思う「こうすれば良かった!」3つのこと
① 大変な時期だけでも宅配ごはんに頼る
毎日ご飯を一から作るのは本当に大変。
年子を連れて、買い物に行くのも一苦労ですよね。
今なら、宅配弁当やミールキットをもっと活用しておけばよかった!と思います。
「罪悪感ゼロ!」くらいの気持ちで頼ってよかったなと感じています。
② 離乳食はレトルトや作り置きでOK
手作りが一番!と思っていましたが、レトルトや冷凍保存に頼っても大丈夫。
まとめて作って冷凍しておくと、毎回の調理がぐっとラクになります。
疲れている時は、市販のベビーフードも無理なく活用するのが◎!
③ ドラム式洗濯機は神アイテム!
高価な買い物なので、我が家も購入をずっと渋っていたんですが…
正直、「一番大変な時期にこそ欲しかった!!!」と、今になって本当に思います。
洗濯物を干す作業って、想像以上に時間も体力も取られますよね。
せっかく子どもが寝てくれたのに、洗濯物をハンガーにかけて干す時間…惜しかったなと。
ドラム式洗濯機は、乾燥までおまかせできるから、休める時間が格段に増えます。
ワンオペ育児の方こそ、導入を強くおすすめしたい家電です!
結局、子どもたちが園に通うようになってから購入したのですが、それでも 「今からでも遅くない!」と思えるほど大活躍しています。
子どもが大きくなってからも出番は続く!
園や小学校に通い始めると、
- 体育の授業
- 連日プールが続く
- 雨の日の泥汚れ
- おねしょ
- 食べこぼし
洗濯の量も頻度も増えます。
ついこないだも、朝に洗濯機を回して水着も一緒に洗おうと思ったら「今日もいるんだった!!」と気が付き、あわてて洗濯機を回しました。
子どもが登校するまでには洗濯から乾燥まで間に合い、ホッとしたと同時に、ドラム洗濯機あって良かったなと思いました。
おねしょもドラム洗濯機があれば怖くありません!
高価でも「時短×体力温存」の価値は絶大
導入を迷っていた頃の自分に言いたいです。
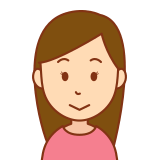
「早く買っとけば、もっとラクできたのにー!」
値段だけを見ると悩みますが、
毎日の“時間”と“ママの体力”を買うと思えば、かなりコスパが良い投資。
特に、年子育児やワンオペのご家庭には本当におすすめです!
私自身、独身気分が抜けないパパとワンオペで育児していた日々でしたが、
振り返ってみて「もっと頼ってよかった」「もっと手を抜いてよかった」と思うことばかり。
ママが元気じゃないと家は回りません!
だからこそ、“できるところはラクする”のも立派な選択。
どうか頑張りすぎずに、共にゆるく・上手に、年子育児を乗り切りましょう!
妊娠中は薬も貼り薬も使えず、本当に辛かったです。
この経験から「育児と体力温存を優先する大切さ」を学びました。
【外出・お風呂】とにかく工夫がカギ!
荷物が多すぎ問題

年子はオムツとミルクの期間が被るので、歳の差きょうだいと比べると荷物は多めになってしまう…!
どこへ行くにもオムツ、ミルク、着替えは2倍。
「2歳差ならもう少し荷物少なかったのかな?」と思う時期も…。
2人抱っこ問題
下の子が赤ちゃんの時、上の子もまだまだ抱っこして欲しい時期。
下の子が歩けるようになっても、両方から「抱っこ!」と言われることもしばしば。
どちらもベビーカーに乗ってくれず、おんぶ+抱っこで公園から帰る日もあり、腰が悲鳴を上げました…。
後ろにおんぶで抱っこ紐。前にこちらのカバンを使って帰宅することも。
《おすすめアイテム》
お風呂は戦場

我が家は基本平日はワンオペだったので、お風呂も毎日1人でこなしていました。
新生児期は里帰りしていたので何とかなっていましたが、自宅に戻ってからは本当にバタバタ!
なかでも お風呂タイムが一番の戦場だったなと今でも思います。
首すわり前は「どう待たせるか」に悩む日々
下の子の首が座るまでは、とにかく試行錯誤の連続。
《おすすめアイテム》
バスマットは赤ちゃんが冷えにくくて滑りにくいので、首すわり前のワンオペ入浴にピッタリでした!
首すわり後は「空気椅子」が大活躍!
下の子の首がしっかりしてきてからは、
アンパンマンの空気でふくらますベビーチェアを使用していました。上の子の時にも使っていました☆
お風呂場に一緒に入れて座らせておける
ぬれても大丈夫な素材なので安心
自分や上の子を洗っている間も見守りやすい
《おすすめアイテム》
この椅子があるだけで、一人で2人を見るハードルがグッと下がりました!
お風呂あがりは“タオルポンチョ”が救世主!
お風呂から上がってからもバタバタですよね。
そんな時、私が本当に助けられたのが
フード付きのタオルポンチョでした!
着るだけで全身の水分をサッと吸収。
✔ フードを被るだけで頭もすぐに乾く
✔ 自分のことは“とりあえず”済ませて、すぐ赤ちゃんのケアへ移れる
《私が購入したのはこれ》
授乳対応タオルポンチョ
ポンチョの横にはフェイスパックをスタンバイ。
貼るだけで“ながらスキンケア”も完了します!
おすすめポイントまとめ
冬場の冷え対策にも◎
授乳口付きなら、そのまま授乳もできて超便利
自分の体調管理や肌ケアも“ちょっとだけ”できるだけで、気分が全然違う!
産後はとにかく自分のことは後回しになりがちですが、
こういった便利アイテムを取り入れるだけで、少しだけラクに、気持ちも軽くなります!
毎日頑張ってるママだからこそ、少しでも手を抜ける工夫を大切にしていきたいですね。
【上の子2歳/下の子1歳】

2人同時にご機嫌ナナメ!どっちも抱っこ期の大変さ。
少しずつ上の子もしっかり歩けるようになり、外出時の荷物も少しラクになってきた…そんな時期。
でも!そのタイミングでやってくるのが、
どっちも「抱っこ~!!」の嵐です(笑)
2人同時に泣かれると、もうパニック!
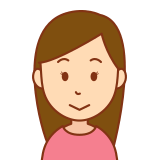
我が家の年子キッズは、午前中はニコニコ。
だけど夕方の一番忙しい時間に2人同時に、くずぐずで大変でした。
洗濯ものを取り入れるのも夕方、晩御飯も作らないといけないのでこちらも焦ります。
夕飯が遅れるとお風呂も寝かしつけも遅くなるので、この時期もかなり大変でした。
正直、1人ではどうにもなりません。
私はそんな時、座って両ひざに2人を乗せて、ゆらゆら揺らすという技で乗り切っていました(笑)
物理的に2人同時に抱っこは無理なので、せめて気持ちだけでも受け止めようと奮闘。
これは年子に限らず、きょうだい育児の“通る道”
年子だから特別…というわけではなく、2歳差や3歳差でも起こる「きょうだいあるある」かもしれません。
でも年齢が近い分、ダブルで甘えたい気持ちが強い時期が重なるのが年子育児の特徴。
ママのキャパは1つだから、本当に毎日が試練ですよね。
そんな時こそ「100点を目指さない育児」を
家の中がぐちゃぐちゃなままの日もある。
ご飯や寝かしつけ、お風呂が遅くなってしまう日もある。
仕方ないと割り切ると少し楽になる。
【上の子3歳/下の子2歳】
上の子が「お姉ちゃん」になり、言葉も通じてきて育児が少し楽に。
ただ、下の子のイヤイヤ期が勃発!
いたずらや「自分でやる!」が増えて、ついイライラしてしまうことも…。
上の子4歳/下の子3歳

年子育児の「超ハード期」もひと段落。
少しずつ心と体に余裕が出てきた時期でした。
夜の授乳もおむつ替えも、夜泣きもなくなり、睡眠時間も増えました。
お風呂に入るのもだいぶ楽に!
2人で仲良く遊んでくれる時間も増え、外出もラクになりました。
2人とも歩けるようになってくると、外出もぐっとラクになります。
ベビーカーの出番が減って、公共交通機関でも身軽に動けるように!
抱っこで腕がパンパンだった日々が懐かしくなるくらい、おでかけのハードルが一気に下がります。
ただし、保育園・幼稚園の入園準備などお金が一気にかかる時期でもあります。
年子育児のもうひとつの特徴は、お金が「連続で」必要になること。
たとえば:
保育園・幼稚園の入園準備
小学校入学・中学校進学
制服・ランドセル・学用品 など…
これらが毎年・連続でやってくるので、資金計画はとっても大事!
お下がりが効かないことも…

年齢差がほぼないからこそ、お下がりが回せない・間に合わないことも。
自転車
キックボードや外遊びのグッズ
制服など
乳幼児期は、お下がりに回せるものが多いのがメリットの1つでもありましたが、大きくなるにつれ、歳が近い分、使いたいタイミングが同じなので、「結局2つ必要になる」というケースも多々あります。
まとめ
✔ 年子を出産する予定なんだけど、どんな感じなんだろう?
✔ 今、年子を育てているけれどワンオペママはどうしているのだろう?
私自身、そんな不安がありました。
年子って珍しいと言われていますが、割と周りにもいるな~という印象です。
みんな口を揃えて「3歳まではとにかく大変!」と言っています。
これは、よく聞くし実感もあります。
だけど、発達や声調面で個人差はありますが、少しずつ手が離れて行き、確実にラクになっていくのも事実です。
私自身、うまく手を抜けず、自身のメンテナンスもせず、7年経った今でも坐骨神経痛は治りません(笑)
でも「手を抜いてもなんとかなる!」と気づけたことは、育児の中で大きな学びです。
育児はまさに長距離走。
無理せず、自分自身のケアも大切にしながら、共に頑張りましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。